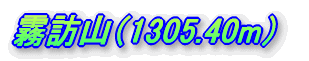
2007年4月15日
長野県塩尻市北小野より
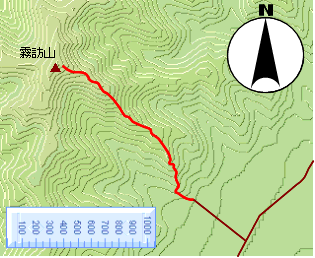
等高線は20m。スケールの単位はm。
(画像のうちいくつかはクリックすると拡大画像を表示します。戻るときはブラウザの「戻る」から。)
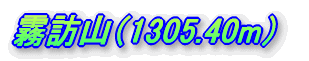
2007年4月15日
長野県塩尻市北小野より
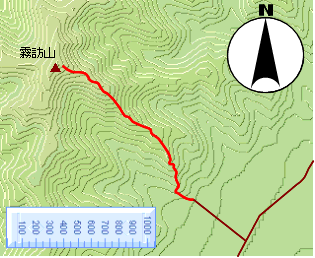
等高線は20m。スケールの単位はm。
(画像のうちいくつかはクリックすると拡大画像を表示します。戻るときはブラウザの「戻る」から。)
 |
 |
 |
|
 |
 |
※霧訪山は標高こそ1300メートルを越すが、登山口からの比高は400メートル少し越すだけの「里山」である。しかし、この比高差に似合わない大展望が待っていて、さらに大芝山への縦走路が開けるなど、最近人気が高い山の一つとなっているらしい。「大展望」「花」「歴史(遺跡と信仰)」の三拍子揃った山といえるが、このうち「歴史」についてはあまり登山者の興味をそそらないのかも知れない。 今回は下山後に平出遺跡を訪ねた。僕が考古学を学び始めた中学生の頃、膨大な平出遺跡発掘調査報告書を手にして圧倒されたことをよく覚えている。しかも考古学にとどまらずに総合学術調査として1950年から行われた発掘調査は、開発を前提とする調査ではなかった。霧訪山を訪ねることがあったら、国指定平出遺跡(平出遺跡公園)と平出遺跡博物館をぜひ訪ねてみて欲しい。 さて、かっとり城跡は別に稿を起こしたので、ここでは平出遺跡について少し触れておきたい。平出遺跡は縄文時代、古墳時代、平安時代の3時期にまたがる大集落遺跡である。縄文時代は中期を中心に61棟以上の竪穴住居跡が検出され、後期には敷石住居跡も発見されている。また、古墳時代から平安時代にかけては128以上の竪穴住居跡と平安時代の掘立柱建物跡が検出されている。 縄文時代研究史で名高いのは、1950年に竪穴住居跡から倒立した状態で埋められた埋甕が検出されたことである。これを契機にして、埋甕研究が始まり、幼児埋葬説、胎盤収納説、建築儀礼説などが議論された。また、中期の平出Ⅲ類A土器として分類された質素な土器は、松本盆地から伊那谷にかけて分布する地域色豊かな土器のタイプサイトとして知られている。 濃尾の私たちにとって忘れてならないのは、平安時代の平出遺跡研究がもたらした成果である。すなわち私たちになじみの深い灰釉陶器だが、灰釉陶器という命名自体が平出遺跡の発掘調査で大量の出土を見たことによって、小山富士夫氏の発案を平出遺跡発掘調査団長であった大場磐雄氏が採用したことによって一般化した(直井雅尚「持ち運ばれた器-灰釉陶器-」(『平出博物館ノート』第20号掲載、2006年))。現在でも白瓷と呼ばれることもある(田口昭二『美濃焼』1983年他)が、平出遺跡の調査を契機として灰釉陶器が一般化したといってよい。平出遺跡の灰釉陶器は東山道によって、生産地である濃尾からこの地に運ばれてきた。一時期混乱した灰釉陶器の編年観などの解決について、消費地である平出遺跡研究が果たした役割は大きい。 灰釉陶器が輸入文物である青磁を模倣して作られたことは周知の通りである。我が国で最初の釉薬を施した灰釉陶器は、おそらくは8世紀中葉以降に猿投で始まったと考えられている。その後9世紀後半に東濃で生産が始まった灰釉陶器は、この信濃へも東山道を通じて大量にもたらされることになるようだ。今回見学した資料に限っていえば、灰釉陶器でも9世紀にまで遡るものは少なくて、10世紀代から11世紀に下る比較的新しいものが多いような印象を受けた。私自身の調査経験のある西濃山間部にもたらされる灰釉陶器から見ると、数型式遅れるという印象が強い。今後の研究を待ちたいと思う。 |
|
←山頂からの展望