
2007年8月5〜8日
山梨県南アルプス市広河原より
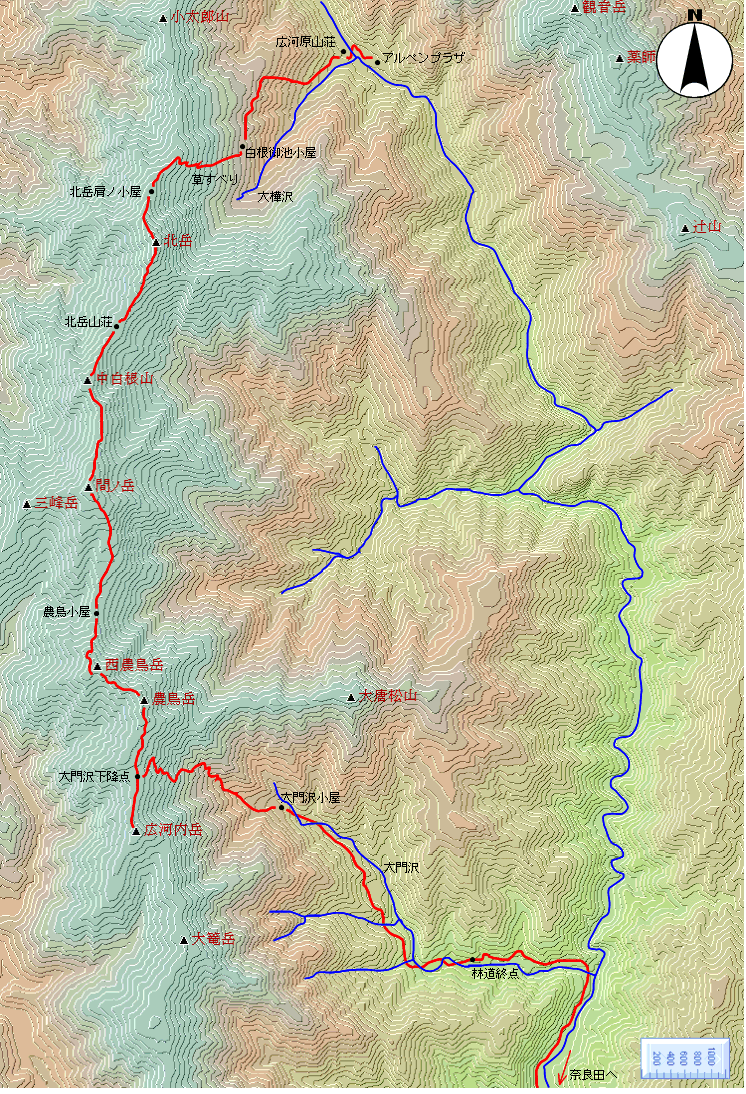
レリーフの等高線は50m。スケールの単位はm。他の山行記録と等高線、縮尺が異なることに注意。
(画像のうちいくつかはクリックすると拡大画像を表示します。戻るときはブラウザの「戻る」から。)

2007年8月5〜8日
山梨県南アルプス市広河原より
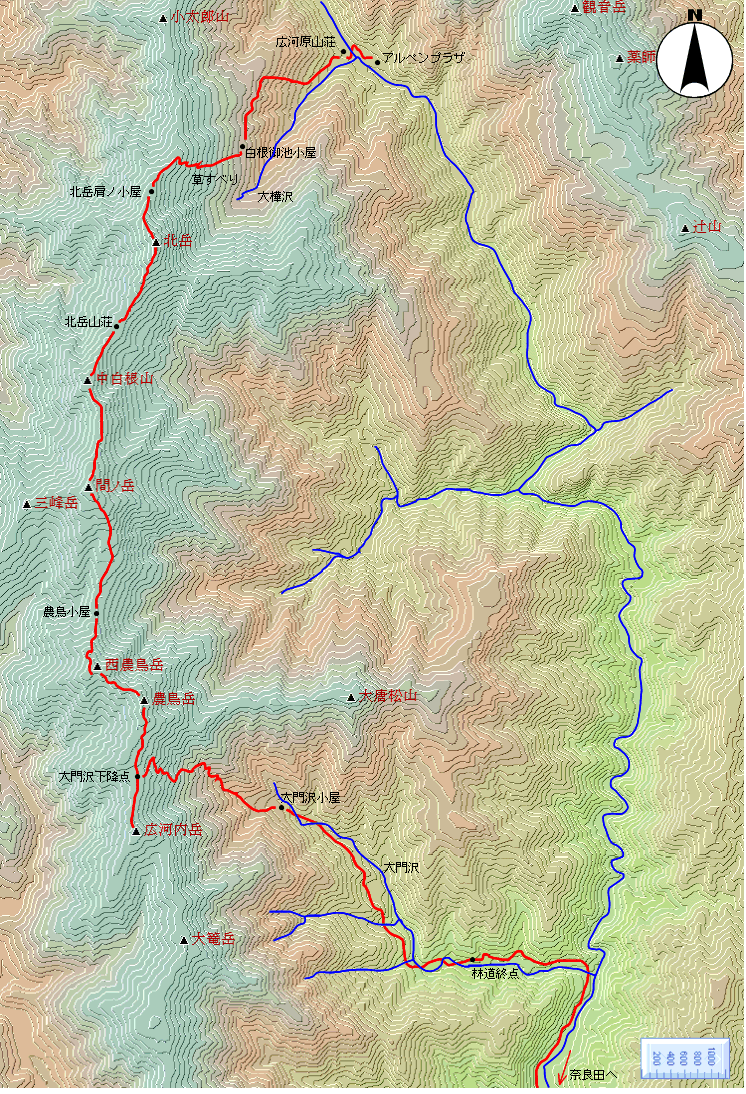
レリーフの等高線は50m。スケールの単位はm。他の山行記録と等高線、縮尺が異なることに注意。
(画像のうちいくつかはクリックすると拡大画像を表示します。戻るときはブラウザの「戻る」から。)
![]() 第1日(広河原〜北岳肩ノ小屋)
第1日(広河原〜北岳肩ノ小屋)
![]() 第2日(北岳肩ノ小屋小屋〜北岳〜中白根山〜間ノ岳〜農鳥小屋)
第2日(北岳肩ノ小屋小屋〜北岳〜中白根山〜間ノ岳〜農鳥小屋)
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
※北岳で滑落した男子学生は、結局は助からなかった。現場を通ってきた登山者の多くが、救助ヘリを振り返っては心配そうに見ていた。リーダーの指示のもとに、しっかり準備体操をしていた姿。リーダーの指示でザックを担いだ面々。礼儀正しく挨拶して出発していった朝の様子を、よく覚えている。滑落現場は、確かに危険な所であり、西側にせよ東側にせよ、滑落したら助からない所だと思われた。しかし、一般道であり、危険を示すトラロープも張られていた。そこで何故事故は起きたのか。今、原因を語る資料を何も持ってはいない。たぶん『山と渓谷』で事故報告がされることになるだろうが、決して他人事ではない。それだは確かだ。ご冥福をお祈りします。 ※農鳥小屋に4時過ぎに着いた中高年の女性のグループがいた。到着したグループに小屋主さんが、「何でこんな時間に着くの。ラジオは持ってるの?ちゃんとアポはとったの?予約の連絡のことだよ。」と矢継ぎ早に聞いていた。南アルプスの稜線の怖さは、過去の落雷事故を見てもわかるはずだ。稜線には落雷事故で亡くなった登山者の慰霊碑が立てられていたり、避雷針があったりと、その様子は他の山域とは少し異なっている。山小屋と山小屋の距離が長い南アルプスは、稜線を歩く距離も長い。いくら森林限界が高いとはいえ、稜線で発雷したらどういうことになるか。これまで御嶽山、針ノ木雪渓、白馬大雪渓と何度も雷の怖さを体験してきただけに、ラジオも持つことがいかに大切か、そして4時過ぎでも雷にあうことなく到着できたということがどれほど幸運なことかは分かるつもりだ。小屋主さんはこのことを言っていたのだった。もし予約の連絡をしたら、到着予定を聞いただろう。それが無理な予定であれば、助言もできたかもしれない。しかし彼女たちにどれぐらい理解されたのか、聞いていてよく分からなかった。何かが変だ。 ※もう一つこの日驚いたこと。北岳山荘を経て中白根山を登っていると、夫婦らしい2人連れの登山者が下りてきた。間ノ岳のピストンですかと聞くと、北岳だと思って登ったら違っていたから戻ってきたと、とんでもないことを話し始めた。何も言葉を返すことができなかった。ちなみにこの山域は指導標もしっかりしているし、朝の内は視程も長く、絶好の山日よりだったのだった。なぜこんなことになるのか、その理由もよくわからない。 ※ポーランド人の登山者は、結局この日大門沢小屋に泊まったことを翌日知った。しかも、大門沢小屋の小屋主さんによると、6時過ぎに到着したとか。まあ、着けてよかった。 |
|
![]() 第3日(農鳥小屋〜西農鳥岳〜農鳥岳〜大門沢下降点〜広河内岳〜大門沢下降点〜大門沢小屋)
第3日(農鳥小屋〜西農鳥岳〜農鳥岳〜大門沢下降点〜広河内岳〜大門沢下降点〜大門沢小屋)
 |
 |
|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
※大門沢下降点に設置されている指導標、というより櫓はさび付いていなかった。手入れが行き届いている感じだったが、一体誰が世話をしておられるのか不思議だった。大門沢小屋に到着した時、奈良田へ下りる途中にくつろぐ登山者の姿に混じって、4人がビールを傾けていた。銀嶺山岳会の人で、聞くと会で下降点の櫓のペンキ塗りを10年に一度やっているとのこと。明日はペンキを塗りに行って、乾く間に農鳥岳まで登ってくる、と話しておられた。その中の1人は富士山の写真を撮りに、1時に出発し、他の3名は3時に出るとか。まさか、と思っていたら本当に1時と3時に出発していった。頭が下がる思いだ。大門沢ルートの急登を、登りに使うというだけで驚きだが、ペンキ塗りとなるとこの道しかないのも事実。登山道を維持するに当たって、さまざまな人の努力があることを忘れてはならない、と強く思った。 ※大門沢小屋からは、意外なことに富士山を真正面に見ることが出来る。南アルプスの主稜線と比べて標高が低いだけに、丸山をはじめとするいくつかの折り重なる稜線を従えた富士山だ。小屋主さんが台風通過直後に携帯で撮影された富士山を拝見したが、思わず息をのむほど美しかった。一瞬携帯であることを忘れるほど美しいシルエットは、ここにおられるから撮すことが出来るもの。いい画像を見せていただき、感謝。 |
|
![]() 第4日(大門沢小屋〜奈良田)
第4日(大門沢小屋〜奈良田)
 |
 |
|---|---|
 |
 |
※奈良田にはかねてから強い関心を持っていた。初めて「奈良田」の名を耳にしたのは、もう30年近く前のことだ。民俗学により深い関心を寄せていたならば、もっと早く知っただろうが、僕は言語を通して「奈良田」を知ったのだった。僕は当時、今は廃村となり水没した徳山村に暮らしていた。その徳山村戸入に特殊促音が残っていることを知った。と、同時に特殊促音は八丈島、伊豆の石廊崎、山梨県の奈良田、長野県の秋山郷、大井川上流の井川にも残っていて、戸入と合わせて言語島として共通するアクセントがあるというものだった(根尾弥七・増山たづ子・大牧冨士夫・久瀬川忠・篠田通弘「徳山村の歴史と文化」『ゆるえ』創刊号掲載、徳山村の歴史を語る会、1982年)。以来、訪ねなければならない地の一つとしてずっと意識してきた。今回このような形で初めて訪れることになったのだが、感慨深いものがあった。 次に奈良田を知ったのは、姫田忠義氏が主宰する民族文化映像研究所が記録した映像、「奈良田の焼き畑」だった。これは早川町教育委員会の依頼により、既に行われなくなっていた焼き畑の民俗を奈良田の人々によって忠実に再現されたのを、1年間通して同研究所が映像化したものだった。これも同研究所から毎号送っていただく『民映研通信』を通してその存在を知るだけだったが、今回、映像のすべてを早川町歴史民俗資料館で観ることができた。映像は生き生きと山に生きる奈良田の人々を映し出していた。奈良田の焼き畑は、ただ単に食料を生産するだけでなく、山という大地から衣食住のすべてをいただくという、大きな精神的循環そのものであることが伝わってきた。この記録映像の全編を観ることが出来たのは望外の幸せだった。今度はしっかりと勉強しに来なければ、と強い思いを抱いた。 ※資料館を見学し終わって、あと40分ぐらいかなと温泉前でバスの時刻を待っていると、疲れ切った様子で中高年の女性2人連れが到着した。同じくバスを待つ女性の下山者が、「姿が見えないからどうされたかと心配していました。」と話しかけると、その2人は、大門沢小屋までたどり着けなくて沢で野宿をして大変だったと話し始めた。ビニールを下に敷いて合羽を着て寝たとか。ツェルトは持っておられなかったんですかと聞くと、そんな重い物は持ち歩かない、とつっけんどんな返事が返ってきた。思わず居合わせた他の登山者と顔を見合わせてしまった。僕が携行しているツェルトは重さ250グラム。500ミリグラムのペットボトルと比べても半分。これまでに一度も使ったことはないが、使わないに越したことはない、と割り切ってザックに放り込んでいる。もし昨晩雨が降ってきたら、もし昨晩が一昨晩のように北風が強い寒い夜だったら、2人は急激に体温を奪われたに違いない。命より重いものなど、どこにもないと思うのだが。バスに乗ってからも単独のテント泊の登山者といろいろ話をした。ひょっとしたらあの2人、ヘッドランプを持っていなかったんじゃないかな、とも。どんなに遅くなっても、ヘッドランプさえあれば歩くことが出来るし、ましてや下降点から大門沢小屋までは白峰三山のメインストリート。指導標もマークもしっかりつけられている。迷い込む心配はない。暗くなって歩けなくなったんじゃないかな、との意見も出た。真相の程はわからないが、最後まで驚きの連続だった山行は、4時間かけて甲府へ戻るバスと電車の旅で終わった。 |
|